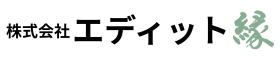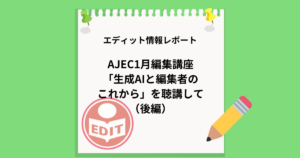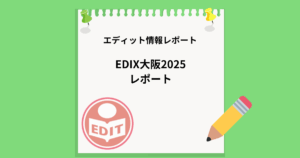EDIX東京2025 見学レポート
4月23日~25日に東京ビッグサイト南展示棟にて開催されたEDIX東京2025に、伊藤は4月24日、25日と見学に出向きました。
業務支援、教材、STEAM学習、ICT機器、教育DXなど7つのエリアに350社以上が出展され、デジタル教科書、個別最適のための教材、生成AI活用事例など多岐にわたる展示に圧倒されました。
30以上の講演・セミナーでは、教育界の第一人者たちが最新動向や事例の紹介をしていました。
EDIXの公式ホームページの下記の記事には、教育現場におけるICT化を進める目的が三つ挙げられています。
◆記事◆ 教育現場のICTとは?メリットや課題、取組事例を紹介
https://www.edix-expo.jp/hub/ja-jp/blog/blog29.html#02
- 情報を収集・活用する力を身につけるため
- ITスキルやIT知識を身につけるため
- 協働的な学びを実践するため
今回、24日の午後に、コニカミノルタジャパン様ブースで開催された『デジタル学習基盤を活用した学習者主体の授業デザイン』(放送大学・准教授/小林祐紀氏)のミニセミナーを紹介いたします。
●デジタル学習基盤を活用した学習者主体の授業デザイン』
放送大学・准教授/小林祐紀氏
日時: 2025/4/24
このお話は、上記1の「情報を収集・活用する力を身につける」に関連する内容でした。
小林氏は、デジタル学習基盤を活用した探究的な学びで育みたいものを≪注意や認知のコントロール、学び方の柔軟さ≫と定義されました。
コニカミノルタジャパン様のtomoLinksという、AI活用による教師の業務負荷軽減と児童生徒の学びをサポートするプラットフォームを活用した事例紹介のなかで、ある小学校の授業の様子を映した写真スライドを見て、驚きました。
「学びの流動性が担保されている」と赤字で書かれたコメントが下部にあるスライドには、教室のなかで子どもたちが自由に立ち歩きながら、話し合っている姿がありました。
よく見ると、タブレットを囲んで語り合うグループがあるかと思えば、一人で教科書とタブレットを見比べて何やら考えている子どももいました。
教師は、子どもがどんな話し合いをしていたり、課題に向き合っているのかを確認するようにして、歩き回っていました。
(ある特定の子どものところに長く留まらないように注意しているとのことでした。)
完全に子どもたちだけで自由に進める授業かというと、そうでもないようです。
まずはこの授業で何を学び、どこをゴールに定めるのかという「授業情報」を教師から子どもたちに共有します。
その後、個別最適な学びに取り組む時間を15~20分確保し、子どもが勝手に学べるような学習環境を整えます。
「授業情報」にある【本時で学ぶべきことがら】【本時で採用すべき学び方】を伝え、子ども自らが選択・決定する学びの機会を盛り込みます。
授業の最後に、子どもが、自分の学び方がどうだったかの振り返りの時間を設定します。
ちなみに、子どもたちからのアンケート結果で、振り返りの時間に大事なものは何かという問いかけに対して、「友達との話し合い」が多くを占めていたことが印象的でした。
写真の場面は、個別最適な学びに取り組む時間の様子でした。
その場面にあるような個別学習活動は、子ども自身が自分の学習方法を調整して最適なものにしようとする場となっていると小林氏は言われます。
小林氏の言われる「学びの流動性が担保されている教室」には、子どもたちの注意や認知のコントロールが育まれる雰囲気があるのかもしれません。
また、その雰囲気のなかで自分に合った学び方を見つけ出そうとする機会を作り出せているのかもしれません。
授業のありようが、教師から児童生徒への一方通行のやりとりから、教師と児童生徒との双方向のやりとりや児童生徒同士のやりとりへと変わってきていることを知ることのできた貴重なセミナーでした。
2025年5月8日 株式会社エディット(文責:伊藤隆)