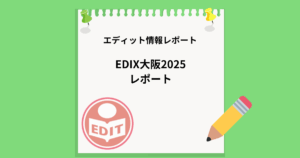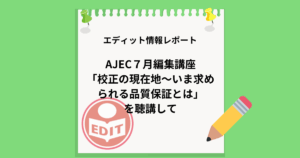日本編集制作協会(AJEC)/ 6月オンライン編集講座 「編集の本質-制作工程と変わらぬ編集者のあり方」を聴講して
日本編集制作協会(AJEC)/ 6月オンライン編集講座 「編集の本質-制作工程と変わらぬ編集者のあり方」
日時: 2025年6月26日(木)18:00~19:30
講師:ベネッセコーポレーション ものづくり推進本部 藤本隆氏
AJEC編集講座の第1回「編集の本質、制作工程と変わらぬ編集者のあり方」は、ベネッセコーポレーションの藤本隆氏による、示唆に富む内容でした。
デジタル化が加速する今、紙媒体の制作工程にこそ編集の基礎が詰まっているという視点から、編集制作の全体像を深く掘り下げていただきました。
今回の講座で特に印象的だったのは、自動音声サービスの目覚ましい進化と、制作工程におけるリードタイムと完成検査の重要性についてでした。
驚くべき自動音声サービスの進化
講演の冒頭で紹介されたGoogleの自動音声サービスには、目を見張るものがありました。
資料をアップロードするだけで、DJのような語り口の男女の掛け合いで音声ガイドを自動生成するというものです。
しかも、資料にない情報までウェブから収集し、自然な会話になるように「えー」や「あー」といった相槌まで挿入するというから驚きです。
藤本氏ご自身も「AIくん、進化しすぎて、ずいぶん喉を節約させていただきました」と語るほど、その完成度の高さに感嘆されていました。
自動生成された内容は、かつて「活字」「写植」といった物理的な制約があった印刷・組版の歴史を振り返りながら、デジタル技術が進化し、いかに情報生成のあり方を根本から変えつつあるかを示すエピソードについてでした。
AIがコンテンツ生成の領域に深く入り込み、そのクオリティが日々向上している現状は、編集者にとって新たな可能性をもたらすものであると同時に、これまでの仕事の進め方を見直す大きな転換期が来ていることを示しているように感じました。
制作工程の鍵を握る「リードタイム」と「完成検査」
藤本氏は、印刷物の制作工程を「川上工程(編集者が汗をかく部分)」と「川下工程(専門の設備やオペレーターが動く部分)」に分け、特に川下工程である組版、製版、印刷、製本では、やり直しが膨大なコストとスケジュール遅延につながることを強調されました。
この「手戻りのない制作」を実現するために不可欠なのが、各工程におけるリードタイムと完成検査の適切な管理です。
リードタイムとは、各工程の担当者が作業を開始するために必要な準備時間のことです。
不完全な原稿やデータの受け渡しは、このリードタイムを不必要に長くし、後続の工程に大きな負担をかけます。
例えば、デザイナーが「本文が長すぎる」「画像の解像度が足りない」といった問い合わせに時間を費やせば、その分デザイン作業に着手するまでの時間が延びてしまいます。
藤本氏は「リードタイムは依頼の仕方の鏡」と述べ、編集者がどれだけ完璧な状態で次の工程にバトンを渡せるかが重要であると話されました。
一方、完成検査とは、各工程の成果物が次の工程へ進むための品質保証です。
プロフェッショナルとしての自信を持って「できた」と返せる状態であり、この検査の精度が低いと、次の工程で問題が発覚し、結局手戻りが発生してしまいます。
編集者自身が行う「検収(検査)」の基準を明確にし、事前に次の工程の担当者と基準を共有しておくことで、円滑な作業の受け渡しが可能になります。
編集者に求められる「扇の要」としての役割
藤本氏は、編集者を「扇の要(かなめ)」と表現しました。
企画者、ライター、カメラマン、デザイナー、印刷会社、製本会社など、多くの専門家や企業が関わる制作において、それぞれのプロフェッショナルは自身の領域を特化しています。
彼らがお互いを直接知らなくても、一つの制作物を完成させられるのは、編集者が「要」として全体を司り、それぞれの専門家に適切な依頼をし、成果を次に正確に引き継いでいるからにほかなりません。
この要の役割を果たすためには、以下の要素が不可欠であると藤本氏は語られました。
- 段取り力:複雑な仕事の流れを整理し、工程を設計する力。
- 交渉力:各工程のプロフェッショナルとスムーズなやり取りを進めるための、相手の専門性への理解とコミュニケーション能力。
- 幅広い興味関心と専門性:担当するテーマや分野に対する深い知識だけでなく、周辺分野や新しい技術にもアンテナを張り、雑学王のような視点を持つこと。
「後工程はお客様」
そして、最も印象的だった言葉は「後工程はお客様」という考え方です。
これは、次の工程を担当する人が、最大限のパフォーマンスを発揮できるように、前の工程の担当者が完璧な準備をする、という意味です。
自分の都合や不手際によって後工程に負担をかけることは、プロとしてはあってはならないという強いメッセージが込められています。
夜中まで作業して「徹夜したぜ!」と喜ぶのではなく、いかに効率的かつスムーズに制作を進め、周囲から「あなたとやると仕事がいつもスムーズだね!」と言われるか。
それが編集者の真のプライドであり、目指すべき姿であると改めて感じました。
AI技術の進化が目覚ましい現代において、紙媒体の制作で培われた「編集の本質」は、デジタルコンテンツ制作にも共通する普遍的な価値を持っています。
藤本氏の講座は、過去から現在、そして未来へと続く編集者の役割と責任について深く考える貴重な機会となりました。
★ご案内★
日本編集制作協会(AJEC)/7月オンライン編集講座
AJECオンライン編集講座、第2回目のご案内です。
今回は、株式会社ベネッセコーポレーションの須藤渉一先生による、編集の実務基礎講座です。
校正をテーマにした回は、毎回人気の講座となっております。
ぜひともご検討いただけますと幸いです。
テーマ:「校正の現在地~いま求められる品質保証とは」
講師:須藤 渉一 (すどう・しょういち)氏
校正工程の基本的な役割や既存の校正記号の確認をしつつ「校正の現在地」はどうなっているのか、そしていま求められる品質保証とはどのようなものであるのかを、事例にもとづき確認していきます。
【こんな方におすすめ】
- 編集業務に関わっている方、編集の仕事に興味・関心がある方
- 編集の実務をより具体的に実践面で知りたい方
- 編集業務に関して一定の経験はあるが、新しい手法を学びたい方
- 日 時:2025年07月24日(木) 18:00~19:30(90分)
- 受講料:2,000円
- 視聴方法:Zoom(オンライン)
https://ajec-koza250724.peatix.com/ - 主 催:日本編集制作協会(AJEC)/教育委員会
- お申込み:こちらのPeatixからお願いします。
→https://ajec-koza250724.peatix.com/ - 問合せ先:AJEC事務局/E-mail:info@ajec.or.jp
2025年7月16日 株式会社エディット(文責:伊藤隆)