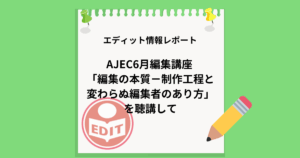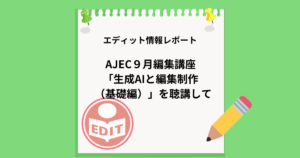日本編集制作協会(AJEC)/7月オンライン編集講座「校正の現在地~いま求められる品質保証とは」を聴講して
日本編集制作協会(AJEC)/ 7月オンライン編集講座
テーマ:「校正の現在地~いま求められる品質保証とは」
日時: 2025年7月24日(木)18:00~19:30
講師:ベネッセコーポレーション ものづくり推進本部 須藤 渉一 氏
ベネッセコーポレーションの須藤渉一氏による編集講座は、デジタル化が進む現代において、校正の本質と編集者に求められる役割を再認識させられるものでした。校正は単なる誤字脱字のチェックではなく、制作物の最終的な「品質保証」を担う重要なプロセスであり、その考え方が揺らいではならないと強調されていました。私が特に感銘を受けたポイントをまとめております。ご一読いただけますと幸いです。
1.校正の根幹をなす「品質保証」の徹底
須藤氏は、「品質向上」と「品質保証」を明確に区別する重要性を説きました。品質向上は原稿制作段階で追求すべきことであり、校正はあくまで品質保証のための《間違いをなくす》作業に徹する必要があります。これにより、後工程での混乱やスケジュールの遅延を防ぎます。
また、円滑な校正作業には、関係者間で「修正判断基準」を事前に合意することが不可欠です。何を修正すべきかを明確にし、どの工程でどこまで修正するかを決めておくことで、判断のブレや無用な修正ループを回避できます。そして、こうした指示を正確に伝えるための校正記号は、デジタル化が進む現代でも、編集者と制作現場をつなぐ重要な共通言語として機能します。
2.デジタル化の波と新たな心構え
デジタル化は、オンライン校正やAIによる自動校正といった新たなツールをもたらし、校正作業の効率を向上させました。しかし、須藤氏はこれに伴う課題も指摘します。PDF上での修正指示は、従来の校正記号のルールに従わない「我流」が増えがちで、意図が正確に伝わらないリスクがあります。デジタル環境においても、相手に確実に伝わる指示を出すという基本姿勢が何よりも重要です。
また、デジタルコンテンツは修正が容易であるという利点がある一方で、一度公開された情報は「デジタルタトゥー」として残り続けます。このため、安易な修正は信用失墜につながる危険をはらんでいます。デジタル時代だからこそ、公開前に完璧な品質を保証するという強い意識が求められるのです。生成AIは強力なアシスタントですが、そのチェック結果を鵜呑みにせず、最終的なファクトチェックは人間の責任として行う必要があります。
3.編集者に求められる「集約」の重要性
校正工程において、編集者には「集約」という非常に重要な役割があります。これは、複数のチェック者から上がってきた修正指示を最終的に判断し、的確で分かりやすい修正指示書を作成して次工程に伝える作業です。この集約作業の質が、制作物の最終的な品質を左右すると言っても過言ではありません。
須藤氏は、優れた集約を行うための「集約の七カ条」を提示しました。
- ファクトチェック: 指摘内容が本当に正しいかを確認する。
- 関連箇所の見抜き: 一つの修正が他の箇所に影響しないかを見抜く。
- 結果の想像: 修正後の全体像を想像する。
- 他人任せにしない: 曖昧な指示を避ける。
- 簡潔さ: 端的で分かりやすい指示を心がける。
- 再確認: 修正指示を入れた後、必ず読み返す。
- 抜け漏れ防止: 全ての指摘を吸収したか確認する。
これらの集約能力は、編集者の力量が最も問われる部分であり、経験とスキルによって磨かれます。デジタル化が進んでも、こうしたヒューマンスキルは決して置き換わることのない編集者の強みだと感じました。
今後、校正工程はデジタルツールの活用によって効率化が進みますが、そのツールを適切に使いこなし、最終的な品質を保証するための「工程設計力」や「デジタルへの知見」を持つ編集者の役割は、ますます重要になっていくのではないでしょうか。
2025年8月7日 株式会社エディット(文責:伊藤隆)