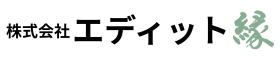株式会社エディット 会長 小林哲夫

教材づくり、本づくりを始めて51年、受注編集の仕事に携わって37年。学習教材や資格書・実用書を中心とした書籍の編集・制作の仕事をさせていただいております。
私は、まず名古屋の地で少しでも長く“文章加工”の仕事をしつづけていきたい、またこの地域で“受注編集”の仕事を成り立たせたいと考えてきました。
その想いが、カタチになりました。
現在、社内スタッフは約85名、外部スタッフも約400名以上と、多くの協力者に支えられて、学校教材と一般書を中心に、編集制作業務を行っています。
さらに、2007年8月より、東京・飯田橋に本格的な「東京オフィス」を開設し、さらに2011年9月に大阪・淀屋橋に「大阪オフィス」をスタートしました。
東京-名古屋-大阪の3拠点のネットワークを活かして、これからも皆さまのご要望にお応えしてまいります。
::: 項目一覧 :::
- 48年の教材づくり、本づくりの経験を活かして
- 幼児ものから小・中・高校向け全教科の学習教材づくり
- 企画・原稿執筆から印刷まで,どの過程からも受注!
- 一般書・実用書・資格本などを編集・制作!
- デジタル編集をいち早く実現!
- 活発になった名古屋の商業的な出版活動
- 定着・安定している学校直販の出版社
- 教材出版社の外注委託ふえる
- 名古屋でも期待高まる編集専門会社
- 実務能力を大切に!
- 編集のファミリーレストランとして
- 企業出版の開発・普及を図る
- 組織づくりと社内の能力開発を柱に
■48年の教材づくり,本づくりの経験を活かして

私どもエディットの仕事の第一の柱は、何といっても幼・小・中・高校生向けの学校教材,塾教材,家庭教材の編集・制作業務です。
私自身の編集稼業は、大阪・東京・京都時代の8か年を合わせて、すでに48年が過ぎようとしています。勤めた出版社は教育図書・教材関係の出版を主とする会社が多く、やはり仕事の中心は幼・小・中・高校の教材づくりでした。
しかし童話や一般書・新聞・雑誌またCD-ROMを使った音声教材・ラジオ講座用テキストあるいは一般の全集ものや図鑑・大型企画本・セット教材など、さまざまなジャンルの仕事を経験し、いつのまにか「本の編集職人」みたいになってしまいました。
さらに名古屋、大阪、東京、京都と渡り歩き、場所によって、いろいろな考え方や仕事のやり方があることを知りました。
また、じつに多くの人にお世話になりました。
おかげで、この仕事にとっていちばん大切な「人とのつながり」もたいへん広くなりました。
そのあと17年間、東京デザイナー学院名古屋校で、編集デザイン科の講師をやりました。
編集プロダクションを経営しながらの週1回の非常勤講師でしたが、それまでの編集放浪時代の体験がけっこう役に立ちました。
こういった経験が出版業界でどれだけ活かせるか、じつはこれが自分の基本的なテーマだと思っています。
■幼児ものから小・中・高校向け全教科の学習教材づくり
(「編集作品」を参照してください)

エディットは、子ども英語教材、知能開発教材、ぬり絵本、絵カード、歌カードといった幼児用の教材から、ドリル・ワーク・テスト・問題集といった教科は5教科だけでなく、音楽・美術・保健体育・技術家庭の実技教科を含めて9教科の教材づくりに携わっています。
小・中・高の学習教材や入試教材・学習参考書の編集・制作をもっとも得意としています。
内部スタッフは、各部門、各教科の専任がいます。セット物、シリーズ物のときは全教科を一括して依頼できます。
幼児ものは、ワールド外語学院の子ども英語教材、中央出版の知育教材、ディスカバー21の「天才ドリル」、増進堂の「幼児のスキルアップワーク(ちえあそび)」などを制作しました。
小学生用は、文溪堂の学校教材やパワー学習、正進社の「国語テスト」「算数テスト」、新学社のポピー「夏ジャンプ」、増進会出版社(Z会)の小学生英語や会員情報誌、自社開発の小学生のための中学準備英語「ハローイングリッシュ」を含めて、多数のワーク・テスト・ドリル・問題集などを手がけています。
中学生用では、ベネッセコーポレーション、東京書籍、Z会、旺文社、学習研究社、光文書院、廣済堂あかつき、創育、学校図書、学宝社、数研出版、新学社、啓林館、教育開発出版、学書、好学出版のドリル・ワーク・テスト等の直販・書店・塾・家販・通販教材や訪販系の大型セット教材、高校入試用はベネッセコーポレーションの中学進研ゼミ「県別高校入試の傾向と分析」や東京学参の「高校別入試問題シリーズ」の仕事をはじめ、各社の入試対策教材を多数つくらせていただいています。
いま名古屋の大手書店に並んでいる「愛知私立高校別入試問題集」は、東京学参さんの委託でエディットが毎年手がけている書店向け入試対策教材の一つです。
また、高校ものは、ベネッセコーポレーションの高校進研ゼミ・英語「エンカレッジ」シリーズや啓林館の理科指導書や「大学入試センター試験」シリーズ、数研出版の教師用指導書、学習研究社のセンター試験対策本、東進スクールの『名人の授業』シリーズなどの仕事をさせていただいています。
■企画・原稿執筆から印刷まで、どの過程からも受注!
(「業務内容」をご覧ください)
教材編集は、ほかの出版物と違ったいくつかの独特の知識・手法・制約があります。
企画一つを取り出しても、準拠ものと標準版あるいはワーク・テスト・ドリルといったジャンルで、基本的に押さえておかなければいけない条件がいくつかあります。
教材づくりの独特さはやはり携わった者でないとわからないところがあります。
ただ言えることは、教材づくりは本づくり・編集技術のあらゆる面が集約された仕事であるといえます。
教科の知識はもちろん取材・文章・表記・デザイン・レイアウト・写真・イラスト・図版・DTP組版・校正・CTP製版・紙・印刷・製本にいたるまでの知識がすべて必要になってきます。
エディットは、これらのノウハウをどの過程からでも提供できる会社です。
現実に、各社版元、クライアントから、企画だけ、原稿だけ、整理だけ、組版だけ、表紙だけ、カタログだけ、イラストだけ、図版だけ、校正だけといったパートの仕事もいくつかやらせていただいています。
■一般書・実用書・資格本などを編集・制作!
(「編集作品」を参照してください)
教材の編集・制作以外に、一般書籍編集部門として、取材・写真撮影・執筆・編集・校正・イラスト・デザインの仕事があります。
あくまで文章を中心とした出版物・印刷物を編集させていただいています。
PHP研究所、ユーキャン、ナツメ社、成美堂出版、双葉社、日本経済新聞出版社、実務教育出版、中経出版さんには、いつもお世話になっています。
また、中央出版の『その時歴史が動いた』シリーズ、青樹社の女性向けインターネットノウハウ集『わくわく』シリーズ、一橋出版の『介護福祉ハンドブック』シリーズ、『環境』シリーズ、『障害者福祉』シリーズ、文溪堂の『小中学生インターネット』シリーズ、中央法規出版の『21世紀の地域づくり』など、シリーズものをいくつか手がけています。
かつては、日本ビクターのCDブック「地球の音楽」全80巻や同朋舎出版の『横浜都市デザインフォーラム公式記録集』『現代・世界の建築家100人』『子どもの運動遊び』、河合塾の『データベースを知る』、名大社の求人案内誌「就職ガイドブック」、S&Tプランニングさんの女性向け月刊誌「ハロージャーナル」、単行本では『民は衣食足りて』『子育ては自分育て』『地球は生きている』『ボランティアの未来』などを編集・制作させていただきました。
最近は、文系・理工系を問わず、各種資格本、検定本、実用書、啓蒙書、図解本、学び直し本などを数多く担当させていただいております。
■デジタル編集をいち早く実現!
エディットの編集部では、かつては「大地」(ジャストシステム)、「QuarkXPress」(クオーク社),「EDICOLOR」(キヤノンITソリューション),いまは「InDesign」(アドビ)のDTPソフトがプレゼンテーションやレイアウトづくり,組版に大活躍しています。
弊社の制作物・編集物はすべて最新のDTPデジタル組版システムでつくられています。
多品種・少ロットこそ出版の本質です。
それに加えて、少コストで期間の短縮を大幅に実現してくれるのがDTPです。
DTPは編集技術の革命と言ってもいいでしょう。
エディットでは、いち早く本格的なDTPを導入して、デジタル組版、デジタル編集、新しい本づくりを軌道に乗せています。
■活発になった名古屋の商業的な出版活動

東京からみた場合、一昔前の名古屋は書籍を中心とした取次ルートの出版活動は皆無に等しかったといえます。
教育書の黎明書房や思想書の風媒社といった専門出版社が独自の思いを持ってがんばっていましたが、その出版規模は大きなものではありませんでした。
しかし最近では、上記2社に加えて、総合教育産業への道を歩む中央出版や「名古屋を起点とした」シリーズで、タウン情報や地域文化を矢継ぎ早に掘り起こし、出版化している勢いのある雑誌系出版社ががんばっています。
KTC中央出版がNHKとタイアップして発行した『その時歴史が動いた』シリーズは、エディットで編集・制作をさせていただきました。
■定着・安定している学校直販の出版社

岐阜・羽島に本社のある小学校教材の老舗の文溪堂をはじめ、中学校教材の浜島書店、学宝社など、学校向けに各種教材を出版したり、学書のように小・中学生用の塾向け教材を発行している学習図書関連の出版社はこの地域に意外と数多くあります。
また、中央出版のように、販売会社から出発して、家庭直販教材の開発・発行で出版社としての基礎をつくり、いま総合教育産業をめざしている会社もあります。
これらの出版社は、出版物が学校教材であり、販売方法も顧客直接販売であるため、名前があまり知られていない会社もあります。
しかし出版社所得ランキングなどを見てもわかるように、会社規模は一般書の出版社やタウン誌類の雑誌社とは比較にならないほど大きく、また毎年の売り上げも定着しており、企業的にもほかのジャンルの会社と比べてたいへん安定しています。
各社とも自社ビルを建設したり、文溪堂のように株式上場したりした会社も出ています。
書店ルートや出版流通の東京集中化・中央集権化に対抗して,名古屋独自の出版活動のあり方を探りつづけた成果であると言ってよいでしょう。
それも、地味で質素でしかも無駄を徹底的に嫌い、冒険をしない名古屋人気質にぴったりの出版商法であることはまちがいないようです。
学校直販の最大のメリットである「発行部数を前もってある程度つかむことができる」という点、それから西にも東にも動きやすい地理的な環境が、名古屋における直販の出版活動を活発にしているようです。
■教材出版社の外注委託ふえる

名古屋の「出版」のおもてだった特徴については、上記のようなことがいえますが、編集・制作面から見た場合、一般書の出版社や雑誌社は、企画から編集・制作・発行業務まで、ほとんどを内部で進めています。
社外を使うとしても、1スタッフとして個人的に仕事を発注する形をとっています。
東京の出版社のように、編集プロダクションのような組織や企業に企画や編集・制作の仕事を委託する会社はまだ名古屋では少ないようです。
しかし学習教材を発行している出版社は、編集・制作業務を外部の専門編集会社に委託する傾向にあります。
すでに25年以上前から自社の半分近い仕事を東京の編集プロダクションに外注している会社もあり、地元名古屋の編集制作会社に対する期待が高まっています。
そのほかの名古屋の出版社も「編集プロダクション」の実態や能力について、少しずつ理解してきており、アウトソーシング(外注化)や共同で本を作っていく姿勢が生まれています。
■名古屋でも期待高まる編集専門会社

名古屋での受注編集の仕事はほとんどが企業PR的な要素を持った雑誌や書籍です。
就職情報誌や不動産情報誌あるいは会社案内的な企業PR雑誌は、この名古屋でも数・量ともに急速に拡大しています。
これらは、かつては広告制作会社やデザイン事務所の片手間の仕事でした。
しかし、今はそうした編集業務を中心とした仕事が主流になってきています。
スタッフも、グラフィックデザイナーからエディトリアルデザイナーが求められ、求人広告も、専門のコピーライターやレポーターを指定する会社が増えています。
いま「名古屋ではデザイナーは食えないが、コピーライターは食える」と言われています。
デザイナーあるいはその卵はたくさんいますが、コピーライター・レポーターといった、取材ができ、情報や文章を加工する人材が少ない、需要に追いつくだけのスタッフの確保ができていないというのが名古屋の現状です。
その意味では、いままさに名古屋は情報や文章の加工屋としての編集専門プロダクションが必要とされていると言えます。
■実務能力を大切に!

学習教材や書籍の編集・制作業務は、ご存知のように,細密かつ煩雑な作業を要求される仕事です。
日程に追われ、膨大な量をこなしながら、1ページ1ページの品質を保っていくことは容易なことではありません。
とくに子どもたちが使う学習図書教材はミスがなくってあたりまえ。
しかし、誤りのない教材をつくることがいかにたいへんな仕事であるかは経験してみればすぐにわかります。
編集者のもっとも大切な仕事は、どんな良い本をつくったらいいかを考えることです。
しかし、執筆された原稿をいかに読みやすい本、わかりやすくミスのない教材に仕上げるかという仕事もわれわれの大切な仕事です。
■編集のファミリーレストランとして

「取材、執筆、写真、レイアウト、なんでもこなせるのがスタッフの条件」と語るのは東京の編プロ「ぐるーぷ・ぱあめ」、「編集者は“時価”であり、その価格は変動する」と教えてくれたのは小沢和一・青春出版社社長です。
編集の仕事はよく「料理」にたとえられます。
いい材料を仕入れ、ほどよく煮たり,焼いたりして、おいしく味付け、それにふさわしい器を用意して、お客様に賞味していただく仕事です。
ならば、編集制作会社は“レストラン”ということになります。
東京の編集プロダクションは高級専門のレストラン。
その分野ではどこにも負けない一流の編集能力を持っていることが大切と言われています。
しかし、地方で継続的に仕事をしていくためには、専門性や特別の技術よりも、ある程度なんでもできる幅広い能力が要求されます。
和食・洋食・中華、なんでも注文に応じて料理ができるファミリーレストラン--まずはそこから出発することになります。
値段もファミリーレストラン並みです。
御用聞きの精神、器用貧乏の心意気を嫌っていては、地方の編集会社は成り立ちません。
こうした姿勢・経験を活かして,いまでは、エディットは質・規模ともに日本有数の幅広い総合編集制作プロダクションに成長しました。
■企業出版の開発・普及を図る

名古屋はこれからの街です。
企業も人も底力を持っています。
戦国武将の三人を例にあげるまでもなく、バイタリティーはどこにも負けません。
ただ、いままでなんとなく「田舎臭い」と馬鹿にされてきたのは「表現力」に欠けたからです。
自分たちの持っているノウハウを相手に伝えることがへただったからです。
強力なメディアも少なく、優秀な表現技術者も、力がつくと、東京へ引っ張られていってしまいました。
しかし、インターネットの普及、電子メールの活用によって、ほとんどの情報がリアルタイムで全国を流れ、クリエーターたちも居ながらにして、中央や全国と直接に仕事ができるようになり、いま名古屋も一気に活性化しつつあります。
この勢いの中で、なんとか企業出版の動きをつくりたい。
出版社の出版活動には限界があります。
とりわけ名古屋ではそうです。
その意味でも、無尽蔵にある各企業のノウハウ・コンテンツを少しずつでも本の形にしたい、ぜひそういう仕事をやってみたいと思います。
■組織づくりと社内の能力開発を柱に
編集プロダクションの生きる道はひとえにヒューマン・ネットワークづくりにかかっています。
1) 執筆・校正・イラスト・図版・デザインなど,フリーランサーたちとのネットワーク
2) 組版(DTP)会社さんや製版・印刷会社さんとのネットワーク
3) 地元プロダクションとのネットワーク
4) 主婦パワーとのネットワーク
これらのネットワークこそ、編集プロダクションの最大の武器です。
エディットでは、いま次のようなスローガンを掲げ、がんばっています。
1) スタッフからディレクターへ
2) ノウハウの客観的な蓄積
3) 発想の転換,前向きの知恵を大切に
4) 合理・公正・協力
5) 職場と自分の活性化
6) 柔軟性と専門性……バランス感覚を磨け
これらは一般企業が社是・社訓としたり、社内教育の標語として掲げたりしているものですが、生産手段は社員一人ひとりの能力だけという編集制作会社にこそ、必要なテーマであり、能力であると言えます。
エディットはこんなことを行ったり、考えたりしている会社です。ぜひ一度、お越しください。