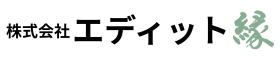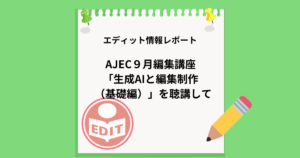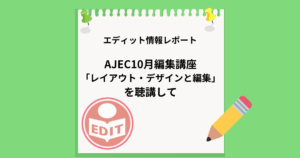「IT WEEK 2025秋」カンファレンス「AI人工知能の進化、生成AIからAIエージェント、そしてその先へ」を拝聴して
2025年10月22日から24日にかけて、千葉・幕張メッセでITとAIの祭典である「IT WEEK 2025秋」が開催されました。この最終日に行われたカンファレンスを聴講しましたので、レポートいたします。
- テーマ: AI人工知能の進化、生成AIからAIエージェント、そしてその先へ
- 講演者: 日本マイクロソフト エバンジェリスト 西脇資哲氏
朝一番から熱量のある講演を繰り広げてくださった西脇氏。生成AIがどのような進化をしているか、そして生成AI使いこなしのあり方について語ってくださいました。以下、半分以上は私の所感ですが、現地レポートとしてお届けいたします。
▼使うことがリスクではなく、使わないことがリスク
生成AIの現在地として、9月12日発表の内閣府「人工知能基本計画」を紹介されました。日本はこれまでも生成AIを規制する方向ではなく、ガイドラインによるゆるやかな縛りで活用を促進しつつ、生成AIを使う時には注意してね、というスタンスでしたが、それでも中国や欧米に比べ、生成AIの利活用や投資が著しく出遅れている状況だそうです。基本計画ではさらに踏み込んで、「AIを使わないこと自体が最大のリスクであり、AI投資・利活用の推進は急務」と書かれています。
https://www8.cao.go.jp/cstp/ai/ai_plan/ai_plan.html
この「AIを使わないことがリスク」との表現は、過日に参加した「Nex Tech Week 2025秋」でのカンファレンスでも聞きました。「このままでは中国や欧米に生産性や経済成長で大きく遅れを取ってしまう」という国家として、経済界としての焦りが見えます。もはや生成AIを異物、異端として恐る恐る触り、石橋を叩いている場合ではない、という心持ちなのでしょう。
編集の世界、ことに原稿作成や問題作成において生成AIをどう上手に使うか、という文脈とは少し違いますので、この部分で我々が必要以上に焦る必要はないと思いますが、それでも編集の周辺業務である「情報の収集、整理」「資料の整形」「データの変換」などの領域では、生成AIの利用が当たり前になっていくことは間違いなさそうです。
▼どの生成AI・LLMを使うのがよいのか
マイクロソフトはOpenAIの最大のスポンサーであり、マイクロソフトが提供しているCopilotもChatGPTがベースですから「それはもちろんChatGPTです」と仰るかと思って聞いておりましたが、回答は「何でもいいんですよ」とのこと。現時点では特定のサービスが突出した性能を発揮しているわけではなく、お互いに拮抗していることが発言の背景にあるようです。
プレゼンテーションではこの1年間、主要な生成AIサービスの性能スコアが上位10社でどう変わってきたかのアニメーションがあったのですが、もう笑うほど抜きつ抜かれつのデッドヒートでした。毎月どころか毎週くらいの勢いで上位が入れ替わり、トップに君臨するAIもコロコロと変わっていきます。「どれを使ってもそんなに変わりません」という状況は、まだしばらくは続くのでしょう。
▼プロンプト・エンジニアリングは過去の遺物?
これも過日、別のカンファレンスで似たような発言がありました。端的には「生成AIの脅威的な進化により、特別なプロンプト技術は不要になりつつある」という趣旨で、西脇氏も「自然会話でAIにお願いし、自然会話で回答が戻る。もうそれで十分な時代に突入した」と仰っていました。
しかし、きっとこの表現が真意を欠いて切り取られ、「もうプロンプトはいらない」が日本中で独り歩きするのだろうな、と思いながら私は聞きました。実際はそうではありません。西脇氏の話の続きを聞くと、「形式にこだわったプロンプトがなくても十分な反応が返るようになった」「くだけた自然言語=話し言葉でも十分に解析されるようになった」という話をされているのであって、「より自在に使いこなす」ための考え方は変わらずに存在しています。
西脇氏も仰っていました。「ワンプロンプトで出てきた回答を見て『使える』『使えない』を決めるのは、生成AIを使いこなせていない証拠です」と。思った通りに行かない、と感じるのは「自分が思っているだけ」であることがほとんどで、伝えて指示する力が足りていないのです、とのこと。耳の痛い話で、「これは生成AIに対してのことではなくて、人と人のコミュニケーションでも同じです」とも仰っていました。
生成AIを利用するときには「一発で100%の結果を出そう」と無理をするよりも、「生成AIといい対話をしながら100%にしていこう」と考える方がよい、とも仰っていました。これは学習用AIなどを構築して全自動で問題生成されるシステムを作ろう、という場合には(一発で間違いのない問題が生成されないとNGなので)相容れない考え方ですが、一般的な生成AIの利活用のあり方としては正しいと私も思います。
▼プロンプトはいらないけど必要(笑)
西脇氏は「プロンプトとかプロンプト・エンジニアリングという言い方が、生成AIの敷居を上げてしまうから嫌い」と仰っているだけで、生成AIからよりよい回答を引き出すためには
・問い立てるチカラ(スライド原文ママ)
・仮説を検証するチカラ
・結果を評価し選択するチカラ
がとても大切、と力説しておられました。この表現はまるで学習指導要領を見ているような気分です。
自分が欲しいゴールに対して、そこまでの手順を細分化する能力の高い人、それを言語化する能力の高い人が生成AIを上手に使いこなせるのです、とご説明くださった勢いで、「つまりプロンプトを積み上げたチェーンプロンプトを考えることが大事なんです」と、思いっきり「プロンプト」を使って説明されていたところが、少し面白かったです。
ちなみにGeminiでもChatGPTでもCopilotでも、我々が質問文を入れるあの窓のことを従来は「プロンプト」の入力と呼んでいたのが、最近はどのサービスも「メッセージ」の入力に変わっているそうです(英語版の表記を言っておられると思われます)。だからと言って「プロンプト」を「メッセージ」と呼び変えてしまうと、語義が広くてコミュニケーションの行き違いを誘発しそうなので、やめておきたいところです。
▼AIエージェントの時代へ
生成AI界隈は目下、絶賛エージェント祭りです。これまでの生成AIとエージェントの違いについて、「どっちも生成AIという点では同じもの」と仰りつつ、コールセンターのチャットボットを例に説明されました。
顧客の問い合わせを解析・理解し、LLMのパラメータの範囲内で回答を生成するのが初期の生成AI。これを社内のデータベースなどと単純に接続したり、添付ファイルで資料を与えたりして、個別の資料を解析・検索・参照した上で回答を生成するのがRAGに代表される最近のAI。それに対して、問い合わせに対して必要な資料や手順をまずリストアップして、そのありかを求めて順に探しにいくのがエージェント。
つまり従来は「何をするか」がある程度明示される前提で、その範囲のことをしていたものが、より曖昧なオーダーに対して「何をすべきか」から思考し、接続可能な情報の中から自律的に探すのがエージェントの基本形のようです。
これに加えて、これまでは言葉や画像で回答を返すだけだった生成AIが、パソコン内のアプリを自動操作したり、Webページの入力や注文を自動操作したりする所までできるようになったことで、俄然注目を浴びているわけです。
生成AIの有効な使いみちの一つとして「プログラム言語の生成」というのは初期からあったのですが、その精度が驚くほど上がったことで、「人が見直さなくてもそのまま動く」レベルのプログラムが次々と生成できるようになりました。この能力を高度に使って、エージェントが動いているというからくりです。
西脇氏自身が作られた「大阪万博エージェント」を紹介しておられました。今までの生成AIでは、「おすすめのイベントを教えて」「効率的な行き方を教えて」のような単発オーダーでの使い方だったのが、会場地図、公式Web、交通機関のWebや混雑状況PDF、運行状況、果てはご自身の予定表データまでをアクセス先として全部串刺しにすることで、「直近の空いている日に行きたいんだけど」と話しかけるだけで、スケジュールの空いている日でイベントに合わせた旅程と見どころオススメ情報を調べ上げ、なんならバスやパビリオンを予約しておきましょうか、と返してきます。実用にはいくつかのハードルがあるものの、もはや恐怖を覚えるほどのエージェントですね。残念ながら万博は終わってしまいましたけれど。
翻って教育の世界で考えると、ひとりひとりの子どもたちに寄り添って学習ガイドをしてくれるエージェントがいる世界はもうすぐそこに来ているのだと思います。このエージェントにキャラクターのアバターを被せた「ドラえもん」や「アトム」の出現も、もうカウントダウンに入っているかのように感じます。
この大きな変化の中で、われわれ編集者には何ができるか。またその一方で、こうしたオールデジタル情報の世界から抜け落ちる生活・学習のシーンや、こぼれ落ちてしまう人、領域が必ずありますから、そこにどのように貢献し続けていけるか。真面目に考えなくてはいけない曲がり角だと感じました。
(企画ソリューション部 藤本)